「計画作成のバラつきをゼロに」――現場が変わる標準化の成功事例2選
2025.07.30A2:導入事例 製造現場における計画作成は、これまでベテランの「経験と勘」に支えられてきました。しかし、現代の製造業では、多品種少量生産や短納期対応、さらには人材の流動化が進む中、属人的な計画作成では安定した生産を維持することが困難になってきています。このような背景から、計画作成の標準化が重要な経営課題となっています。本記事では、生産スケジューリングの役割を踏まえつつ、コニカミノルタメカトロニクス株式会社、フジシート株式会社の実例を通じて、課題・解決策・成果とともに、標準化を成功させるポイントを解説します。
製造現場における計画作成は、これまでベテランの「経験と勘」に支えられてきました。しかし、現代の製造業では、多品種少量生産や短納期対応、さらには人材の流動化が進む中、属人的な計画作成では安定した生産を維持することが困難になってきています。このような背景から、計画作成の標準化が重要な経営課題となっています。本記事では、生産スケジューリングの役割を踏まえつつ、コニカミノルタメカトロニクス株式会社、フジシート株式会社の実例を通じて、課題・解決策・成果とともに、標準化を成功させるポイントを解説します。
計画作成標準化の重要性
計画作成の標準化には、以下のような効果があります。
- 属人化を排除し、再現性のある業務プロセスを構築することで、教育時間を短縮し業務リスクを軽減できます
- 計画修正が瞬時に行われ、変化に即応できるスピード感のある運用が可能になります
- 業務の見える化により改善活動が促進され、将来的なDX推進のための基盤整備にもつながります
つまり標準化とは、単に手順を定めるだけでなく、継続的な改善を支える仕組みづくりそのものなのです。
生産スケジューリングの役割
計画作成の標準化を推進する上で、生産スケジューラは中心的な役割を果たします。従来のExcelや紙ベースの管理とは異なり、スケジューラは以下の点で業務の標準化を支援します。
- 設備や作業員の能力を考慮した、有限能力な計画作成が可能
- 工程間の整合性を保った多工程のスケジュールを自動生成
- マスタ情報(BOM・作業時間など)との連携により高精度な計画
- ルールの定義・適用が可能なため、例外処理の標準化も実現
属人的だった判断を、システムに組み込むことで、計画業務が誰でも実行可能な形に変わるのです。
事例で学ぶ成功のカギ
事例①:コニカミノルタメカトロニクス~段取り時間を22%削減
課題 : 工程間の調整が非常に複雑であったため、どうしてもベテラン担当者による手作業に頼らざるを得ない状況が続いていました。製品ごとに工程や必要となるリソースが異なることもあり、計画業務の属人化が進行していたのです。その結果、現場では調整作業に多くの時間が費やされ、納期遅延のリスクも常に抱える状態となっていました。
解決策 : AsprovaとSolverを導入して、製品ごとの仕様や工程、リードタイム、治具の有無、段取り時間といった要素を網羅的に考慮した、スケジュールの最適化を目指しました。
成果 : Solverを導入して、計画作成にかかる時間は大幅に短縮され、かつ、段取り時間を22%削減しました。属人的な作業が減少したことで、計画業務の教育が簡素化され、新たな担当者への引き継ぎもスムーズに行えるようになり、人材の流動性に対する対応力も強化されました。 [事例記事]
事例②:フジシート~生産計画にかかる時間を90分から15分に短縮
課題 : 多品種生産の特性上、製品ごとの工程が複雑に入り組み、日程調整が非常に煩雑になっていました。そのため、製造部門と営業部門との連携がうまくいかず、納期に対する認識のズレから、顧客への回答に不一致が生じることも少なくありませんでした。さらに、生産負荷にバラツキが生じることで、現場では作業の段取り変更や対応に追われる状況が頻発し、混乱が生じていました。
解決策 :営業との納期調整もスムーズ化、部門間の連携強化、多品種対応による日程調整の煩雑さを解消するためAsprovaを導入しました。BOMや工程、設備などの情報を一元管理し、スケジュールの自動化と見える化を進めました。
成果 : 営業部門と製造部門との間で納期調整がリアルタイムで可能となり、受注活動がスムーズに進むようになりました。その結果、現場では計画に基づいた作業が安定して実施できるようになり、混乱が減少して生産性が向上しました。さらに、製造・営業・調達の部門間の情報共有と意思疎通が促進され、全社的な最適化の視点で生産計画を運用できる体制が整いました。 [事例記事]
計画標準化を成功させる5つのポイント
1) 現場の暗黙知を可視化 : ベテランが担っている判断基準や調整ルールを棚卸しし、文書化・データ化します。これが「標準化」の出発点です。
2) ルールをシステム化 : 作業手順や優先順位、例外処理などをスケジューラのパラメータとして設定し、ルール化します。これにより、人によるばらつきがなくなります。
3) 例外処理のナレッジ化 : 「急な注文が入ったときどうするか」「機械が停止した場合の対応」など、従来は現場判断だった対応をルールとして整理し、誰でも対応できるようにします。
4) 現場を巻き込む導入ステップ : スケジューラ導入と標準化は、現場の理解と協力が不可欠です。担当者が納得し、自分ごととして使ってもらえる工夫が成功の鍵です。
5) 計画と実績の差異を検証・改善 : 標準化は一度で完成するものではありません。計画と実績のズレを毎月レビューし、ルールを見直していくことが継続的な改善につながります。
まとめ:標準化は“強い現場”への第一歩
計画作成の標準化は、単なる業務効率化ではなく、「人に依存しない強い現場づくり」を意味します。属人化から脱却し、再現性・柔軟性・改善性のある計画業務を実現することで、製造現場は変革を遂げることができます。
そのためには、生産スケジューラというツールを上手に活用しつつ、現場の知恵をルールとしてシステムに反映させることが求められます。標準化は、未来の変化に強い工場づくりのための「基盤」なのです。
コラム編集部
最新記事 by コラム編集部 (全て見る)
- 在庫が不足する“その時”を予測する~Asprova新機能紹介 - 2026年1月28日
- 作業を押し込んで割り付ける~裁量の利くプログラムを開発 - 2025年12月10日
- ユーザーが語る新たなAsprova~ユーザー会2025~ - 2025年12月3日

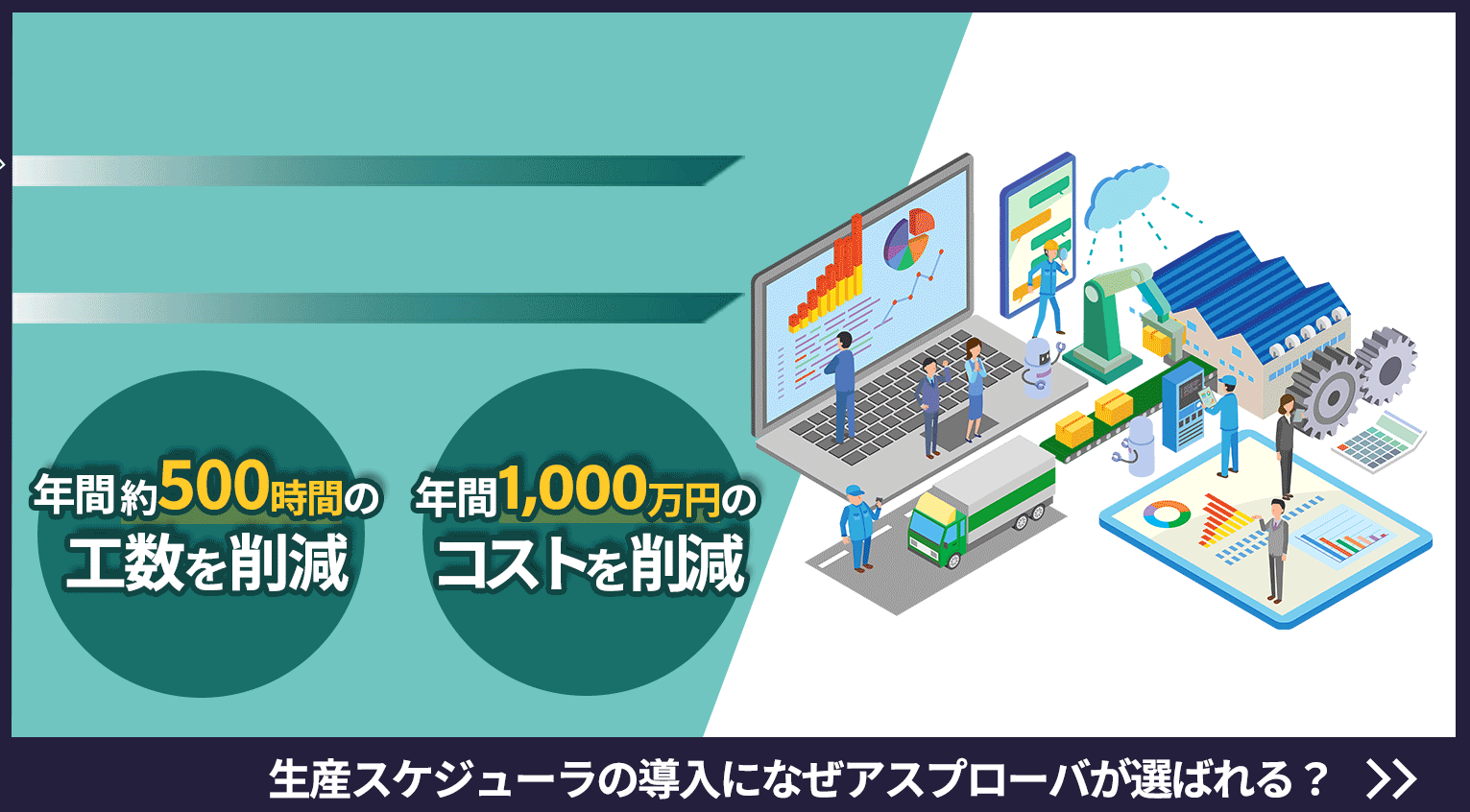
 在庫もラインも止めない!今すぐ始めたい原材料手配の最適化術
在庫もラインも止めない!今すぐ始めたい原材料手配の最適化術 “なんとなく管理”からの脱却!デンカが語る、見える化による現場改善ストーリー
“なんとなく管理”からの脱却!デンカが語る、見える化による現場改善ストーリー 「1日が数時間に短縮!」――計画立案のスピードが劇的に変わった2社の事例
「1日が数時間に短縮!」――計画立案のスピードが劇的に変わった2社の事例 「納期遵守率95%超」ぺんてる・ナブテスコが語る、生産スケジューリング成功の裏側
「納期遵守率95%超」ぺんてる・ナブテスコが語る、生産スケジューリング成功の裏側 2週間→1週間!パナソニック式リードタイム半減の秘密
2週間→1週間!パナソニック式リードタイム半減の秘密 脱属人化の事例~経験や勘頼みから脱却した生産スケジューリングを実現!
脱属人化の事例~経験や勘頼みから脱却した生産スケジューリングを実現!