生産計画とは?立て方と立案時の注意点
2024.02.13A1:生産計画・スケジューリング
製造業における生産計画とは、製品を滞りなく生産するために不可欠なものです。製造業の業務サイクルは、取引先との契約内容に合わせて製品を製造し、出荷して売上にするのが基本です。より売上をアップするためには、品質維持はもちろん効率的に業務サイクルを循環させる必要があり、それぞれの工程でいかに業務を最適化できるかが問われます。製品の品質を維持しつつ業務工程を最適化するためには、入念な計画を立てておき、計画にもとづいた業務管理やコントロールが必要なのです。
今回は、生産計画の基礎知識をはじめ、生産スケジューリングとの違いや計画立案時における注意点などを解説します。また、生産計画の立案を効率化するツールとして、生産スケジューラのメリットについてもご紹介します。
【目次】
■生産計画とは?生産スケジューリングとの違いも紹介
■生産計画の種類
■生産計画の立て方
■スケジューリングする際の注意点は?
■生産計画の効率化におけるシステム導入のメリット
■まとめ
生産計画とは?生産スケジューリングとの違いも紹介
生産計画とは、広義には製品の生産・製造に関わるすべての計画の総称です。日本工業規格(JIS)では、「生産量と生産時期に関する計画」と定義されています。より具体的にいうと、以下のことを決定するのが生産計画です。
- どの製品を
- どの時期に
- どれだけの量で
- いつまでに生産して
- いつ出荷するか
このように、製品の生産量と生産時期・納期を決める計画を指します。これまでの生産情報や販売状況、受注情報などをもとに必要な材料・部品を調達し、スケジュールを決定します。その後、製品の生産へと移るケースが一般的です。製造から出荷に至るまでの日程はすべて生産計画の対象となります。こうした生産計画にもとづいて、人員計画や資金計画などを立案します。適切な生産計画が立てられていれば、生産ラインの健全化につながります。納期の遵守や在庫の適正管理、材料調達の効率化などの効果も期待できます。
生産スケジューリングとの違い
生産計画と似た用語に、「生産スケジューリング」があります。生産スケジューリングとは、生産計画をもとに各工程の作業手順を計画する作業のことです。生産スケジューリングは、生産計画のうちに含まれる作業のひとつと考えると良いでしょう。生産スケジューリングでは「◯日◯時までにこの工程を完了させる」というように、人員や機械設備などのリソースとその作業量を時間軸上に配置し、スケジューリングしていきます。作業量と時間軸、用意できるリソースを可視化する作業であり、有限能力スケジューリングと呼ぶケースもあります。
生産計画の種類
生産計画は、大きく「押し出し方式(PUSH型)」と「引っ張り方式(PULL型)」の2種類に分けられます。
押し出し方式(PUSH型)
押し出し方式(PUSH型)は、事前に立てた生産計画をもとに各生産を進める方式のことです。シンプルな計画方式であり、「生産量がある程度安定している」「需要予測が比較的立てやすい」という製品であれば、押し出し方式の生産計画が適しています。 押し出し方式は計画通りに進めやすいというメリットがありますが、突発的なトラブルや変化に弱いというデメリットもあります。デメリットを補うために、過剰在庫を抱えやすい傾向にあります。
引っ張り方式(PULL型)
引っ張り方式(PULL型)とは、商品量や納期の工程を買い手側から生産側に向けて計画する方式のことです。顧客からの受注数などから逆算して生産計画を立案するため、過剰在庫を抱えにくいというメリットがあります。顧客へ直接製品を販売するメーカーがよく採用している方式です。例えば、自動車メーカーのトヨタはPULL型方式の考え方をベースにした「カンバン生産方式」を実践しています。下工程から送られてくる「カンバン(=製造する商品の商品名や品番などが記載されているカード)」の量をもとに生産ラインを稼働させ、必要な分だけ製品を製造する方式です。
生産計画の立て方
生産計画は「大日程計画」、「中日程計画」、「小日程計画」の3つに分けて立案します。長期スパン・中期スパン・短期スパンの生産計画をそれぞれ立案することで、生産計画の大きな流れをより細かなアクションに落とし込めるようになります。以下の表で、各計画の違いを簡潔にまとめました。
| 項目名 | 大日程計画 | 中日程計画 | 小日程計画 |
|---|---|---|---|
| 概要 | 必要な資源(ヒト・モノ・カネ)を用意するための計画 | 資源(ヒト・モノ・カネ)の使い方を決めるための計画 | 現場間での生産指示を具体的にするための計画 |
| 計画の期間 | 6ヶ月~数年規模 | 1ヶ月~6ヶ月 | 1週間~1ヶ月 |
| 計画の内容 | 人員計画の立案 資金計画の立案 設備計画の立案など |
人員の手配 月別生産計画 部品・原材料の調達計画など |
部門や人員のジョイン 作業指示書の作成など |
ここからは、大日程計画・中日程計画・小日程計画それぞれの違いを解説します。あわせて、スケジューリングの方法である「フォワードスケジューリング」「バックワードスケジューリング」についてもまとめました。
大日程計画
大日程計画は、6ヶ月~12ヶ月 、または数年規模の生産計画です。対象期間は長いですが、基本的に毎月作成する生産計画です。過去の受注実績や納品量などをもとにこれからの受注量や納品量を予測し、設備投資計画や人員計画などを立てていきます。1年後を見据え、既存製品の改良や新製品の開発を計画するのも、大日程計画の一部に含まれます。 大日程計画の要は、需要予測です。大日程計画は必要な人員や資金、機械設備などの資源を確保するための計画であるため、各資源を確保するための根拠を需要予測から導き出さなくてはなりません。市場調査の結果や過去のデータなどをもとに需要予測をしたうえで、予測結果にもとづいた資源を確保していきます。
中日程計画
1ヶ月~6ヶ月 の生産計画が中日程計画です。顧客から受注した内容をもとに、生産量や生産ペースを計画していきます。人員手配や在庫計画など、1ヶ月単位で考える計画内容が多い点が特徴です。このことから、「月次計画」と呼ばれることもあります。 中日程計画では、月別の生産計画をはじめ材料の調達計画、現場のシフトを鑑みた中長期的な人員配置などが行われます。一度立てた計画は週ごとに見直しを行い、都度修正を行いながら計画を実践していくケースが一般的です。
小日程計画
小日程計画は、1週間~1ヶ月間 の短期スパンを対象とした生産計画です。毎日もしくは毎週のペースでどの作業をするかを決定し、いつまでに作業を完了するかなどを細かく決めていきます。納期をもとに、日ごと・週ごとの工程手順を決めたり、人員配置をしたり、現場に合わせた作業指示をします。3種類の計画のうち最も複雑化している計画で、全体の流れを熟知している従業員でなければ立案が難しいという面も。しかし、緻密な小日程計画が立てられれば、人員や機械設備の稼働率を上げ、生産リードタイムを短縮する効果も見込めます。
フォワードスケジューリング
フォワードスケジューリングとは、生産を開始する日程をあらかじめ決定し、最初の工程から順に計画を立てるスケジューリング方法です。「前倒し計画」と呼ばれることもあります。最初の工程(生産開始日)を基準に各工程の作業時間・日数を決め、最終的な納期を決める方法と考えると良いでしょう。
バックワードスケジューリング
バックワードスケジューリングとは、納期から逆算して計画を立てるスケジューリング方法です。納期に近いタイミングから生産に着手できるため、完成した製品の在庫を抱える期間を短くできるメリットがあります。フォワードスケジューリングとは対照的に、「後倒し計画」とも呼ばれます。納期が事前に決まっている場合は、バックワードスケジューリングの手法を使うのが一般的です。
スケジューリングする際の注意点は?
生産計画を立てる際に留意しておくべきポイントを、以下でご紹介します。
生産計画に無理や無駄がないか
生産計画は、人員や機械設備などのリソースや作業負荷、材料の調達など様々な要素を踏まえて正確に立案しなくてはなりません。納期に間に合わせようと無理な計画を立てると、人員や機械設備への負担が大きくなり事故につながる可能性もあります。かといって、納期に余裕を持たせすぎるとリソースを持て余してしまい、企業の生産性や競争力の低下を招いてしまいます。複数の要素を踏まえたうえで、現場のリソースに即した生産計画を立てる必要があるのです。その性質から、豊富な知識や経験、現場で培ったノウハウなども求められるため、立案作業が属人化してしまっているケースも少なくありません。
機械の故障をはじめとするトラブルへ対処できるか
生産計画を立案しても、必ずしも計画通りに作業が進むとは限りません。機械設備が故障したり、人員に変動があったりすると生産に影響が及びます。特に機械設備が故障すると、生産が完全停止してしまうこともあります。日常的な設備保全を行うことは大前提として、突然の故障や生産ラインのストップに備えてスケジューリングすることも求められます。
このほか、在庫情報や販売計画、原価計画など生産計画で留意しておくべき要素は様々です。顧客のニーズも多様化し、手作業による生産計画の立案が難しくなっています。そこで重要なのが、アナログではなくデジタルな方法で生産計画を立案すること。生産管理システムや生産スケジューラなどのツールを導入し、効率化することが負担軽減のヒントです。
生産計画の効率化におけるシステム導入のメリット
生産計画を最適化できれば、製造リードタイムの削減をはじめ、リスクへの柔軟な対応やスピーディで的確な対応ができるようになり、競争力の強化にもつながります。各種ツールやシステムを導入し、生産計画を効率化することで得られるメリットを、以下で4つピックアップしました。
業務効率化と生産性向上
生産スケジューラや生産管理システムには、登録したマスタや連携したシステムからデータを参照し、生産計画を自動生成する機能が搭載されています。これによって生産計画にかかっていた工数を大幅に削減でき、生産性の向上が期待できます。「生産計画にリソースが割かれており、ほかの重要な業務に集中しにくい」といった課題を抱えている現場であれば、業務の効率化に伴いコア業務にも集中しやすくなります。
人的ミスの削減
生産計画を手作業で立案していると、人的ミスや遅延が生じやすくなります。また、急な依頼への対応が困難になったり、工程ごとの状況や計画内容が共有しにくくなったりします。その結果、計画に必要な情報がブラックボックス化することも考えられるのです。
生産管理システムを導入すれば、複数人で作業を行っても、入力したデータがリアルタイムで集約・更新されるため、全員が工程や在庫状況などを正確に把握できるようになります。
在庫管理の精度向上
生産管理システムには、在庫状態や生産状況などをリアルタイムで確認できる機能が搭載されています。これにより、生産不足や過剰生産などのトラブルを事前に防げるのが強み。余剰在庫を抱えるリスクの回避や在庫金額の削減にもつながるでしょう。また、在庫管理の精度が向上すると材料や部品などを適切なタイミングで調達できるようになります。全体の生産性向上や納期の短縮も期待できるでしょう。
属人化の解消
生産管理システムや生産スケジューラであれば、複数の要素や制約を踏まえた適切な生産計画をスピーディに立案できます。これにより、属人化の解消が見込めるでしょう。属人化が解消されれば、従業員のノウハウやスキルをより広い場面で活かしてもらうことも可能です。
まとめ
生産計画は、ものづくりの各工程の効率化や生産性の向上など、重要な役割を果たします。だからこそ、製造現場では効率的な生産計画を立案することが求められるのです。とはいえ、複雑化する生産計画を手作業で進めることは難しいもの。そこで重要なのが、各種システムやツールの活用です。
アスプローバの生産スケジューラは、様々な条件に対応可能な柔軟な計算ロジックにより、属人的な計算式を排除するだけでなく、Excelだと何時間もかかる計画立案作業を自動でこなすことができます。これにより、生産計画立案にかける時間、および計算ミス訂正等に割く作業時間を大幅に減らすことができます。
また、設備や人員の稼働状況、負荷状況など、生産現場の状況を把握しながら、リソース配分や設備の稼働状況の調整など、迅速な対応も可能となります。することができるので、生産現場の状況を把握しながら、リソース配分や設備の稼働状況の調整など、迅速な対応も可能となります。
アスプローバの生産スケジューラ導入によって、具体的にどのような業務改善が実現したのかはこちらのページをご確認ください。
コラム編集部
最新記事 by コラム編集部 (全て見る)
- なぜこの2社は計画のブレを最小限にできたのか?精度向上のカギを解説 - 2025年7月2日
- “半日が10分に短縮”も可能に!属人化を脱し、計画作成を効率化した方法とは? - 2025年7月2日
- “なんとなく管理”からの脱却!デンカが語る、見える化による現場改善ストーリー - 2025年7月2日

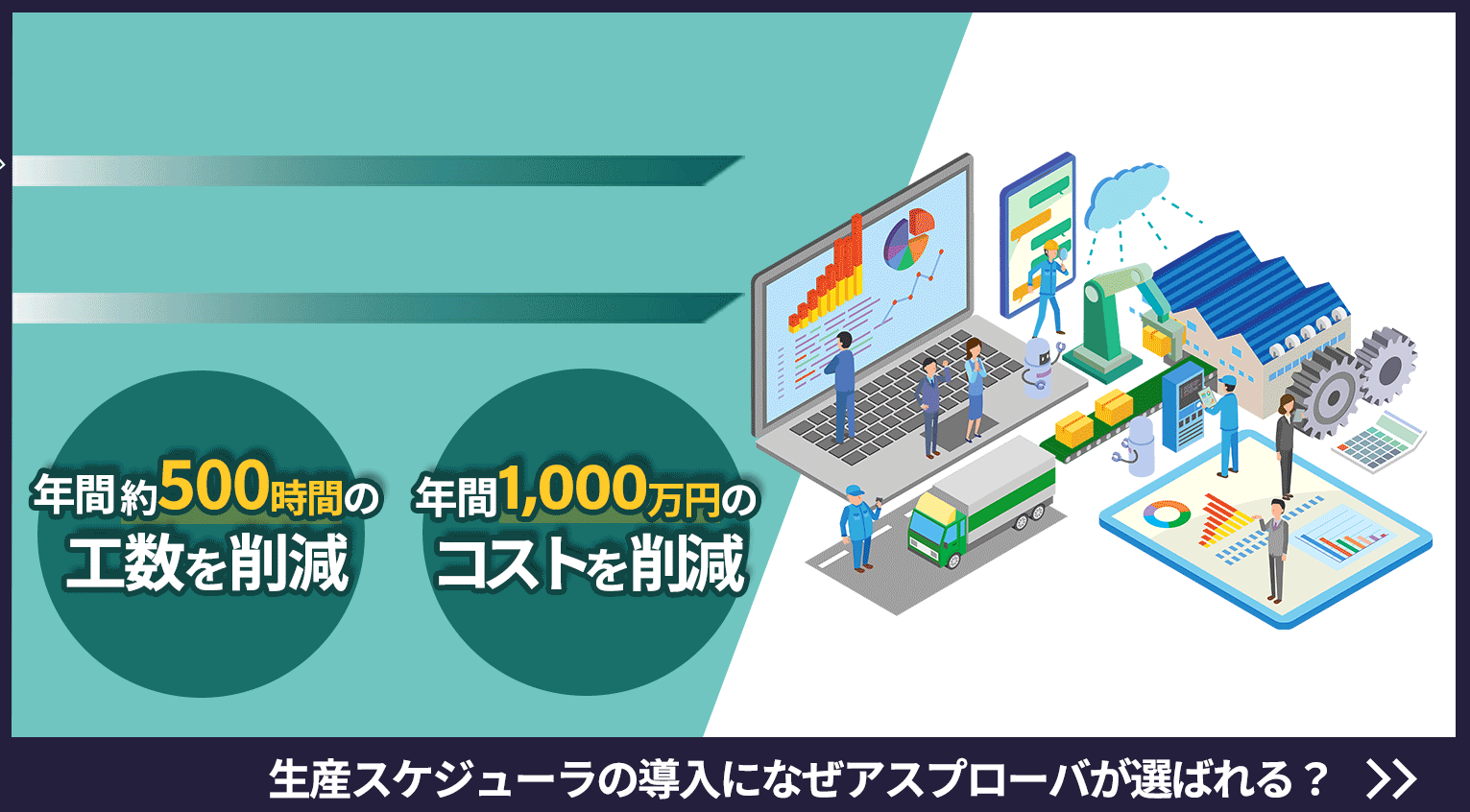
 【可動率(べきどうりつ)の基礎知識】稼働率との違い・可動率を向上する方法とは
【可動率(べきどうりつ)の基礎知識】稼働率との違い・可動率を向上する方法とは 初のウェブシステム~使いやすさが飛躍的に向上 Asprova My Schedule発表会
初のウェブシステム~使いやすさが飛躍的に向上 Asprova My Schedule発表会 お客さまの要望から生まれたAsprova新機能 「マーカー」 ガントチャートを見やすく
お客さまの要望から生まれたAsprova新機能 「マーカー」 ガントチャートを見やすく 生産スケジューラとは?導入するメリットと導入時の注意点を解説
生産スケジューラとは?導入するメリットと導入時の注意点を解説 生産管理における「生産スケジューラ」とは
生産管理における「生産スケジューラ」とは 歯車製造など金属加工における生産スケジューラ活用方法
歯車製造など金属加工における生産スケジューラ活用方法