「必要なときに必要な量だけ」――原材料手配のムダをなくした現場改革の実例
2025.07.30A2:導入事例 製造業において、原材料手配は単なる購買業務ではありません。計画、現場、物流、そして経営成果までをつなぐ重要な“動脈”です。特に多品種少量生産や短納期対応が求められる今日、原材料が「ない」「届かない」「多すぎる」といった事態は、現場の混乱や納期遅延、そして収益悪化に直結します。
製造業において、原材料手配は単なる購買業務ではありません。計画、現場、物流、そして経営成果までをつなぐ重要な“動脈”です。特に多品種少量生産や短納期対応が求められる今日、原材料が「ない」「届かない」「多すぎる」といった事態は、現場の混乱や納期遅延、そして収益悪化に直結します。
本記事では、ニデックサーボ株式会社とニデックエリシス株式会社の事例を通じて、生産スケジューリングを活用した原材料手配の適正化手法をご紹介します。
原材料手配の重要性
原材料手配は、「必要なときに、必要なだけ、正確に届く」ことが理想です。しかし現実には、
- 余剰在庫によるスペースと資金の浪費
- 欠品による生産中断
- 緊急調達によるコスト増加
- 突発的な変更に追従できない手配体制
など、属人化や計画との乖離により多くの課題が発生しています。
特に短納期・高変動の製造環境では、事前に立てた計画がすぐに変わり、そのたびに手配も見直さなければなりません。これに対応するには、「計画」と「手配」を一体運用することが不可欠です。
生産スケジューリングの役割
生産スケジューラは、原材料手配を適正化するための要です。なぜなら、スケジューラが作成する計画には「いつ・どの製品を・どのラインで・どの順に生産するか」が明確に定義されており、それに基づけば「いつ・どの部品を・どれだけ必要とするか」が正確に導き出せるからです。スケジューラを活用することで、
- 所要量の自動計算と発注リストの自動出力
- 手配のタイミングと数量の最適化
- 計画変更に伴う即時対応
が可能となり、手配精度が飛躍的に向上します。
事例で学ぶ成功のカギ
事例①:ニデックアドバンスドモータ株式会社~生産計画の固定率が40%から90%に
課題:少量多品種で納期が厳しい中、Excelベースの管理では対応に限界がありました。変更が頻発するにも関わらず、手配リストが手作業で作られていたため、ミスや遅れが多発していました。
解決策:Asprovaの導入により、生産計画が変わるたびに、部品の所要量と発注タイミングが自動的に更新されるようになりました。Excelによる属人管理を脱却し、手配業務が標準化されました。
成果:生産計画の固定率が40%から90%に向上することにより、原材料の安定供給が実現しました。また、変更があっても即座に反映されることで、手配ミスが激減。在庫を持ちすぎず、必要な時期に必要な量を手配できるようになり、在庫回転率が大幅に向上しました。[事例記事]
事例②:ニデックエリシス株式会社~製品在庫保有日数30%以上減
課題:新製品立ち上げ時、品目や部品構成の頻繁な変更により、手配部門が最新情報に追いつかず、現場での部品不足が頻発していました。また、発注のタイミングも手配担当者の経験に頼っており、属人化と抜け漏れが課題でした。
解決策:Asprovaを導入し、BOM展開と生産スケジュールを基にした部品所要量計算を自動化しました。さらに、ERPとの連携により、発注処理までを一気通貫で行う仕組みを構築しました。
成果:変更情報が即座に手配へ反映されることで、新製品立ち上げ時の混乱が激減。必要部品のリストが常に最新化されることで、部品不足によるライン停止がなくなりました。生産計画立案時間を40%短縮、製品在庫保有日数30%以上減が実現しました。 [事例記事]
成功の4つのポイント
- 導入前にマスタを整備し、導入後も定期的なメンテナンスを行う体制が必要です。
- 「計画は生産部門、手配は調達部門」という縦割り運用では、情報の伝達ロスが起こります。スケジューラが出す情報を部門共通の“単一の真実”とすることが鍵です。
- いきなり全品目・全工程に適用するのではなく、重要品目や特定ラインからスモールスタートし、成果を見える化して全社展開するステップが有効です。
- 「納期遵守率」「手配リードタイム」「在庫日数」などのKPIを可視化し、PDCAを回すことで、導入効果を持続的に高めることができます。
まとめ
多品種少量・短納期・変化対応、現代の製造現場において計画通りに原材料が揃うことはもはや奇跡ではなく、仕組みで実現するべき必然です。属人的な購買管理を卒業し、スケジューラと連動した原材料手配の適正化は、企業の競争力に直結します。
コラム編集部
最新記事 by コラム編集部 (全て見る)
- 在庫が不足する“その時”を予測する~Asprova新機能紹介 - 2026年1月28日
- 作業を押し込んで割り付ける~裁量の利くプログラムを開発 - 2025年12月10日
- ユーザーが語る新たなAsprova~ユーザー会2025~ - 2025年12月3日

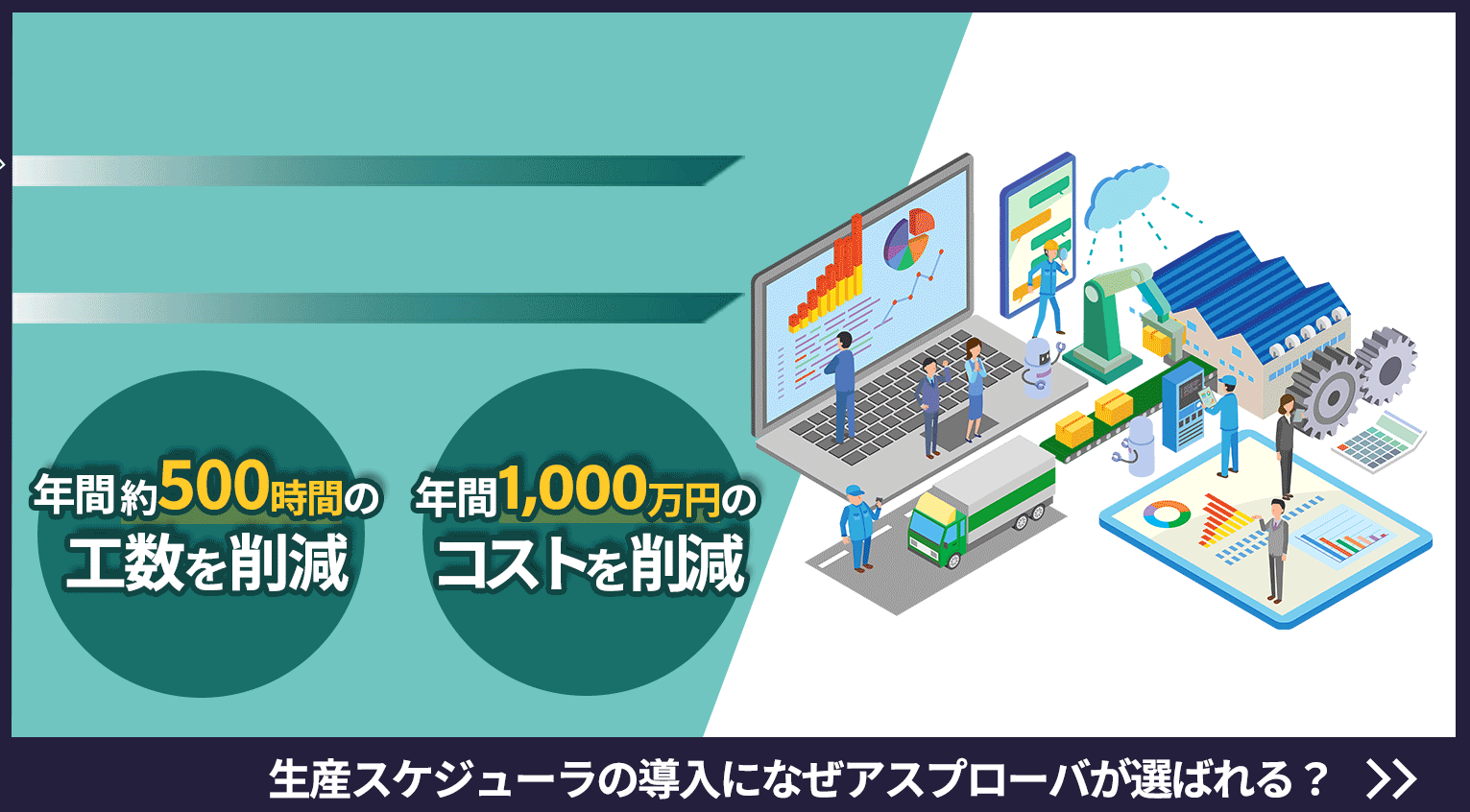
 在庫もラインも止めない!今すぐ始めたい原材料手配の最適化術
在庫もラインも止めない!今すぐ始めたい原材料手配の最適化術 なぜこの2社は計画のブレを最小限にできたのか?精度向上のカギを解説
なぜこの2社は計画のブレを最小限にできたのか?精度向上のカギを解説 “半日が10分に短縮”も可能に!属人化を脱し、計画作成を効率化した方法とは?
“半日が10分に短縮”も可能に!属人化を脱し、計画作成を効率化した方法とは? “なんとなく管理”からの脱却!デンカが語る、見える化による現場改善ストーリー
“なんとなく管理”からの脱却!デンカが語る、見える化による現場改善ストーリー 「1日が数時間に短縮!」――計画立案のスピードが劇的に変わった2社の事例
「1日が数時間に短縮!」――計画立案のスピードが劇的に変わった2社の事例 倉庫が半分に!岡本製襪×住江織物の在庫削減リアルストーリー
倉庫が半分に!岡本製襪×住江織物の在庫削減リアルストーリー