急な需要変動も怖くない!計画変更を爆速化する秘策とは?
2025.07.30A2:導入事例 製造現場では、激しい需要変動やライン増設、海外展開などに伴い、生産計画変更の必要性が頻繁に発生します。従来の手作業では、変更のたびに膨大な工数と専門知識が必要となり、計画の精度や応答速度が低下しがちです。本記事では、生産スケジューラを活用して迅速な計画変更を実現したTOYO PACK KIYAMA株式会社とパナソニック株式会社 ホームアプライアンス社の事例を紹介しながら、その重要性、スケジューリングの役割、成功のポイントを解説します。
製造現場では、激しい需要変動やライン増設、海外展開などに伴い、生産計画変更の必要性が頻繁に発生します。従来の手作業では、変更のたびに膨大な工数と専門知識が必要となり、計画の精度や応答速度が低下しがちです。本記事では、生産スケジューラを活用して迅速な計画変更を実現したTOYO PACK KIYAMA株式会社とパナソニック株式会社 ホームアプライアンス社の事例を紹介しながら、その重要性、スケジューリングの役割、成功のポイントを解説します。
迅速な計画変更の重要性
生産現場での計画変更を迅速かつ多頻度で行うことは、競争力維持・コスト最適化・顧客満足度向上の観点から不可欠です。計画変更できないと、その結果、生産リードタイムが長くなり在庫が滞留し、キャッシュフローや倉庫スペースを圧迫します。突発的な受注の増減や設備トラブル発生時に迅速に対応できないと、納期遅延によるペナルティや顧客離れを招くリスクが高まります。マーケット環境の変化にリアルタイムで追従できる体制づくりは、グローバルサプライチェーンにおける柔軟性と回復力を高めます。
生産スケジューリングの役割
生産スケジューラは、設備や作業員などのリソースの制約条件を考慮しながら、最適なリソースの割り振りや作業順序を自動算出し、以下のような役割を果たします。
- 計画立案の工数削減 : 従来は手書きやExcelで数名が何日もかけて行っていた生産計画の作成・修正を、生産スケジューラによる自動計算に置き換えることで、計画立案工数は大幅に削減します。これにより担当者の負担が軽減され、より戦略的な業務へリソースをシフトできます。
- 即応性の強化、生産リードタイム短縮 : 高速シミュレーション機能によって、需要変動や突発的な変更要求にも瞬時に最適解を提示できるようになります。これにより、週1〜2回しか行えなかった計画の見直しを、毎日または随時実施できるようになり、生産リードタイムの半減や納期回答の迅速化を支援します 。
- 脱属人化、情報共有 : 工程マスタや制約条件をシステムで一元管理し、ガントチャートなど画面上での可視化を通じて、経験や勘に頼らない標準化された計画立案体制を構築します。これにより、担当者交代時のリスクを低減し、現場全体で同じ情報を共有しながら改善活動を行う基盤を提供します。
事例で学ぶ成功のカギ
事例① TOYO PACK KIYAMA株式会社~計画作成工数を1/2以下に削減
課題 : PETボトルラインを新設した際、従来のExcelと属人的な管理方法では計画作成に多大な時間を要し、工程間の調整でも頻繁に計画ずれが発生していました。また、熟練者しか使いこなせないノウハウが属人化を進めたことで、人員交代時のリスクが増大していました。
解決策 : Asprovaを導入し、缶およびPETボトル充填ラインの工程マスタと制約条件をシステム化しました。自動スケジューリング機能により投入順序や設備負荷を考慮した最適計画を数分で算出できるようになり、導入当初は既存ラインのみを対象に段階的に適用して安定動作を確認した後、順次展開を進めました。
成果 : 従来のExcelでの生産計画に比べて計画作成工数は半減しました。さらに、属人化リスクを排除、登録制約の自動整合性チェックでミスはほぼゼロになりました。週2~3回発生していた計画修正の負荷を大幅に軽減し、生産稼働率が向上し、かつ、担当者のワークライフバランスも改善されました。[導入事例]
事例② パナソニック株式会社~生産リードタイムが1/2に
課題 : IHジャー炊飯器基板実装ラインでは需要変動が大きく、週に2度の手書きと旧スケジューラによるスケジュール見直しに4名が2日間を費やしていました。その結果、ガントチャートを書き直す必要が生じ、変更のたびに現場が混乱し、納期回答が遅延する事態が頻発していました。
解決策 : Asprovaの自動計算機能を活用して、設備制約や段取り、ロットサイズをマスターに登録しました。旧システムからのデータ移行後にはスケジュールパラメータを綿密にチューニングし、リアルタイムでの再計算が可能な運用体制を構築しています。さらに、定期的な運用レビューを通じてルールの改訂を行い、継続的な計画精度の向上を推進しています。
成果 : 計画立案時間は「4名2日から2名1日」に短縮、週2回から週5回への迅速対応を実現しました。生産リードタイムは約2週間から1週間に短縮され、応答性が飛躍的に向上しました。さらに計画精度の向上に伴い、在庫削減と設備稼働率の改善を同時に達成し、コスト構造が最適化されました。[導入事例]
生産スケジューラ導入の成功のポイント
- 導入目標の明確化 : 何を改善したいのか(例:計画作成時間の短縮、納期遵守率の向上、在庫削減など)を定量的に設定し、現状とのギャップを可視化します。明確なKPIがあることで、導入効果の評価や社内合意形成がスムーズになります。
- 制約条件の洗い出し : 設備能力や段取り時間、最小・最大ロットサイズ、製造順序ルールなど、現場の暗黙知をすべて洗い出してシステムに登録します。洗い出し時の精度が高いほど、スケジューリングの精度が向上します。
- 段階的な導入 : 全ライン一斉適用ではなく、まず特定のラインや工程でパイロット運用を行い、安定した稼働を確認してから他ラインへ横展開します。小さな成功体験を積むことで、現場の理解と協力を得やすくなります。
- 現場とITベンダーの継続的なコミュニケーション : 導入前後に現場担当者、設備管理者、生産技術者などと定期的にレビュー会議を実施し、運用ルールのずれやシステム設定の最適化を図ります。双方向のフィードバック体制を築くことで、変更要望にも迅速に対応できます。
- 継続的なPDCAサイクル : システム導入後も定期的に計画結果と実績の差異を分析し、パラメータやマスタ設定をアップデートします。操作研修やハンズオンセッションを継続的に行い、現場スタッフのスキルを底上げすることで、安定した運用とさらなる改善を実現します。
まとめ
変動対応力の強化は、グローバル競争力の源泉です。Asprovaのような高性能生産スケジューラを活用し、迅速な計画変更を実現することで、リードタイム短縮や工数削減、納期遵守率向上といった多面的な効果を得られます。本記事のポイントを押さえ、貴社の生産現場での導入・運用にお役立てください。
コラム編集部
最新記事 by コラム編集部 (全て見る)
- 在庫が不足する“その時”を予測する~Asprova新機能紹介 - 2026年1月28日
- 作業を押し込んで割り付ける~裁量の利くプログラムを開発 - 2025年12月10日
- ユーザーが語る新たなAsprova~ユーザー会2025~ - 2025年12月3日

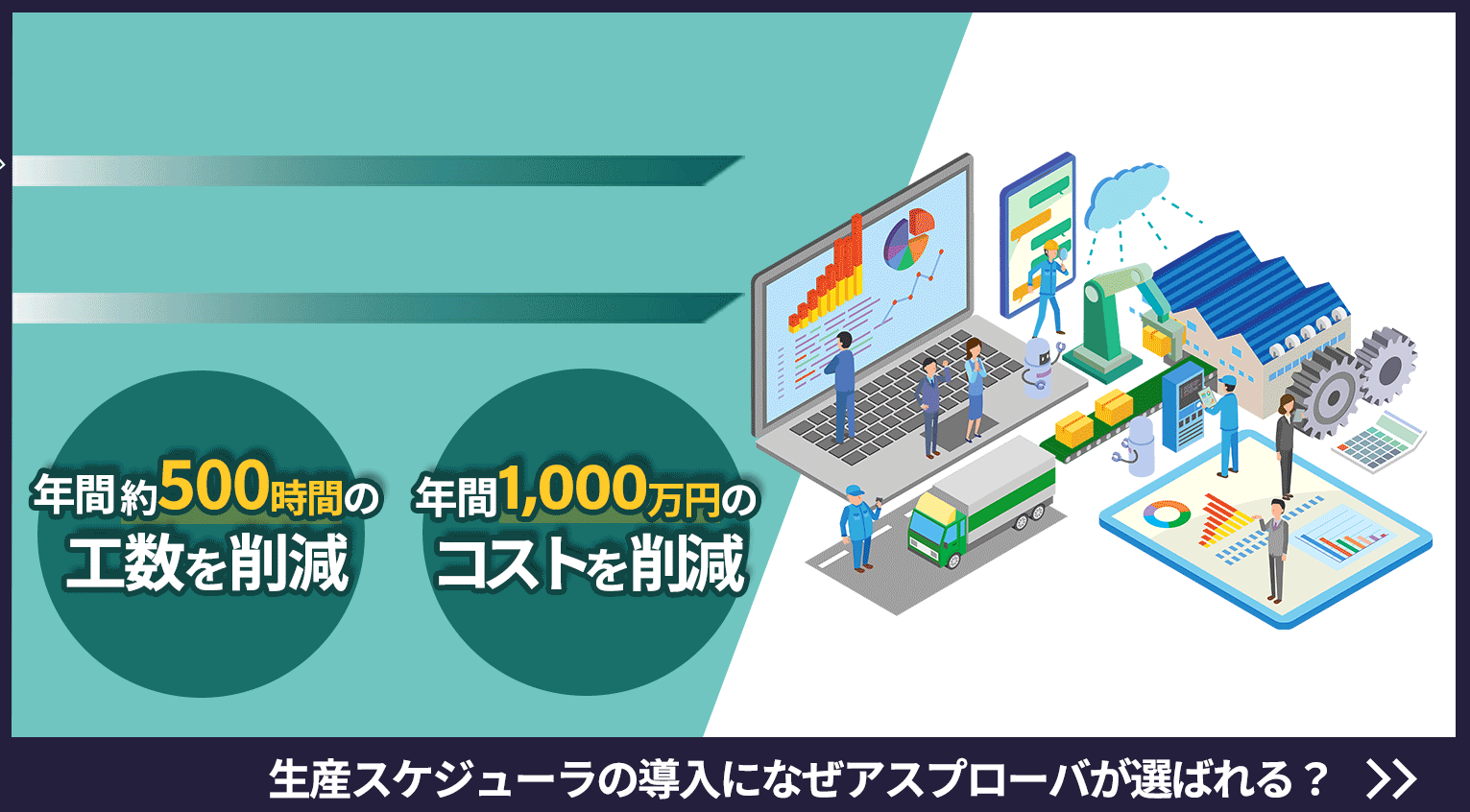
 “半日が10分に短縮”も可能に!属人化を脱し、計画作成を効率化した方法とは?
“半日が10分に短縮”も可能に!属人化を脱し、計画作成を効率化した方法とは? 「1日が数時間に短縮!」――計画立案のスピードが劇的に変わった2社の事例
「1日が数時間に短縮!」――計画立案のスピードが劇的に変わった2社の事例 「納期遵守率95%超」ぺんてる・ナブテスコが語る、生産スケジューリング成功の裏側
「納期遵守率95%超」ぺんてる・ナブテスコが語る、生産スケジューリング成功の裏側 受注生産計画~在庫管理システム×スケジューラ連携で納期遵守率を向上
受注生産計画~在庫管理システム×スケジューラ連携で納期遵守率を向上 段取り時間を削減し、納期遵守率を上げる!生産KPIの実践活用法
段取り時間を削減し、納期遵守率を上げる!生産KPIの実践活用法 情報共有の事例~生産スケジューラ導入で開発工期80%削減!
情報共有の事例~生産スケジューラ導入で開発工期80%削減!